ケジラミ症とは?症状はどんなもの??
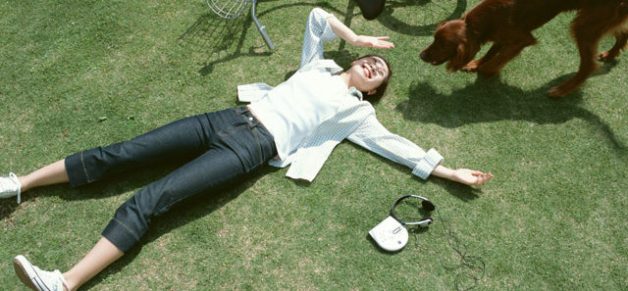
ケジラミ症とは主に性行為で感染する感染症です。
吸血性の昆虫であるケジラミ(Phthirius pubis)が陰毛などに寄生することにより発症し、ケジラミは主に陰毛に寄生しますが、他にも肛門周囲、腋毛、胸毛、太ももの短毛、鬚、睫毛、眉毛や頭髪にも寄生してしまいます。
ケジラミは幼虫から成虫まで、ヒトの血液を吸って栄養にしており、また、ケジラミはヒトにだけ寄生し、ヒトからだけ吸血します。
血液を1日に数回吸って成長し、脱皮を繰り返して成虫となり、成虫となったメスは交尾した後に産卵します。
その際、卵を毛の根元の近くに産み付け、毛の基部近いほうにセメントのような物質で固定します。
卵は7日前後で孵化し、5~6日で脱皮します。
その後、8~11日で成虫となり、そのまた1、2日後には産卵し始めるようになります。
その成虫は3~4週間生存しますが、その間に30~300個の卵を産むと言われています。
ケジラミの成虫の体長は、メスで1.0~1.5mm、オスで0.8~1.0mmです。
体の色は褐色を帯びた白色であり、楕円形である頭ジラミに対して円形に近い形で、頭部は小さいが触覚を2本持ち、身体には3対の脚を持ちます。
一対目の脚の先端には細い爪があります。そして、残りの脚の先端にあるカニのような大きな爪で陰毛をつかみますが、この大きな爪を持つことから蟹ジラミ(crab lice)とも言われています。
ケジラミの潜伏期間は1~2ヶ月くらい
ケジラミは1日のほとんどを毛の根元で静止したまま過ごし、毛の根元をつかんだままであまり動かず、皮膚から血を吸います。
動く場合も普通は毛にしがみついて移動しますので、ノミのように跳んだり跳ねたりすることはありません。毛がないところでの移動は苦手ですので、自分ではほとんど動けず、もし動いたとしても1日に移動可能な距離は最大で10cmくらいとなっています。
また、人の体から離れたとしても48時間ぐらいは生存できますが、それ以上経過すると餓死してしまいます。
ケジラミの潜伏期間は1~2ヶ月くらいであり、感染してから1ヶ月くらいで症状がでる人が多いようです。
ケジラミの主な症状は激しいかゆみですが、これはケジラミへのアレルギー反応によるものであるため、ケジラミに感染しても最初はかゆみはありません。
しかし、ケジラミが増えてくるとかゆみが出始め、最初は軽いかゆみですが、ケジラミの数が増えるのに従ってだんだんとかゆみが強くなっていき、また、かゆみだけでなく、軽い痛みを伴うこともあります。
強いかゆみが特徴のケジラミですが アレルギーの反応は人によって異なるため、かゆみの程度にはかなりの個人差があります。
数匹の毛じらみがいるだけで激しいかゆみを感じるような人もいます。
普通だとかなりケジラミが増えないとかゆくはなりませんが、たまに数匹の毛じらみがいるだけで激しいかゆみを感じるような人もいます。
このような人の場合、潜伏期間が4~5日ぐらいと非常に短くなる可能性もありますが、逆に、たくさんケジラミがいるのに、全然かゆみを感じないという人もまれにいるようです。
また、ケジラミに感染しても、皮膚に発疹等が出ないというのも特徴ですが、激しいかゆみのために皮膚をかきむしり、皮膚に傷ができて湿疹ができるということはあります。
その他、特徴的な症状として、下着に点状の茶色い粉が付着するというものがあります。
この茶色い粉の正体は、ケジラミが人から吸って栄養とした血液の糞便となっています。
また、稀にケジラミがまつ毛に感染することがあります。
この際の症状としては、ケジラミが目やにのように見えたり、目の周辺の違和感を感じたりすることがあります。
そして、このまつ毛に感染した場合は、目に薬が入ってしまうため、治療に薬が使えなくなります。
そのため、ピンセットで虫体と卵を1個ずつ除去するようになるため、とても手間のかかる作業になってしまいます。
ケジラミ症は主として性行為などの直接接触によって感染します。
しかし、寝具やタオル、浴場の脱衣かごなどにより間接的に感染するということもあります。
明らかにケジラミ症の自覚症状がある場合は、医療機関で早期診断を行うことをおすすめします。
ケジラミ症は簡単に他人へ感染し、相互感染を繰り返すことや家族内で感染することもあるので、セックスパートナーや家族全員の治療も行う必要があります。
衣服は熱処理またはドライクリーニングを行うようにし、感染を防ぐようにしましょう。









